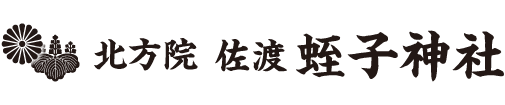歴史The History of Shugendō
修験道の歴史
修験道は7~8世紀に大和葛城山で修行していた呪術者、役小角(えんのおづぬ)によって開創されたと伝承されています。
奈良・和歌山・大阪には役小角が開基したと伝わる寺社が多数存在しています。
活動拠点は、葛城山・大峰山・金峯山・熊野三山以外にも富士山・羽黒山・湯殿山・英彦山・御嶽山・大山・白山など全国各地に存在しました。
江戸時代 僧侶は神仏習合山岳信仰との関連が深く、修験道との結びつきが強く、修験山伏は全国に20万人以上いたと推定されます。
明治期に修験道禁止令が出された際に失職した修験者は約18万人いたとされます。
徳川幕府は修験山伏を統制する為に「修験道法度」を制定し、当山派(真言宗醍醐三宝院)と本山派(天台宗聖護院)に所属するように義務付けました。
山伏は霊山に入峰し、山に伏して修行を積み庶民の健康安全を加持祈祷し信仰の指導者(先達)となり村民を引き連れて各地の霊山へと登拝しました。

葛城二十八宿修行風景
佐渡の霊山 金北山、壇特山、金剛山も明治までは女人禁制の修行場として真言密教の霊場として栄えました。
山中には修験道の開祖役小角と聖宝理源大師の石像が祀られています。
佐渡三山を吉野 大峰 熊野と見立て「三山駈け」修行が行われていました。
この様に山伏は庶民からの信頼が高く信仰の中心的存在でありました。
現在でも全国の修験山伏は護摩祈祷を行い、昔と同じ様に庶民のお願い事をお祈りしています。

修行道の看板